みなさん、こんにちは!石ちゃんです!
ここ何年かでLEDという言葉を耳にしたり、見かけるようになったことが増えたかと思います。
「LED」という言葉は認知したけれど、それが一体どういう物でなぜ耳にするようになったのか…
私もみなさんと同じような疑問を持っていたので、今回はLEDについて深掘りしていきたいと思います!
LEDってそもそも何?
LEDとは Light Emitting Diode の頭文字をとっています。直訳すると、発光ダイオード。要するに、LEDは電気を流すと発光する半導体ってことなんです。
いや、半導体ってなんなの⁉ってなりますよね…笑
半導体とは!全ての電子機器に入っているほど重要な部品 です!
物質には電気を通す導体と、電気を通さない絶縁体に分けられます。半導体は、導体の半分という意味で、電気を通すときと通さないときがある仕組みになっています。
この仕組みによって電気を制御できるのが半導体です。
実はこの半導体、電子機器の普及率が上がり需要が世界的に高まっているため2022年現在は半導体不足が発生しています。
全ての電子機器に入っているほどですから、エアコン・洗濯機・もちろんスマートフォンにも使用されていて、照明だけでなく、多方面に生産遅れを引き起こしています。
半導体についてもっと詳しく知りたいという方は、以下の記事が参考になります!
半導体とは?なぜ不足しているの?誰にでもわかりやすく図解します【菅製作所】
ここまでで、LEDのそもそもの部分については少しお分かりいただけたでしょうか!
LEDの生まれ(歴史)
最近、第○世代という言い方が流行っていますが、
(お笑いの第七世代だったり、2022年はKPOP第四世代到来!だったり)
実は照明界にも世代があります!
- 第一世代:ろうそく
- 第二世代:白熱電球
- 第三世代:蛍光灯
- 第四世代:LED
その中でもLEDに関しての歴史をまとめると、以下のようになります。
| 西暦 | できごと |
|---|---|
| 1907年 | イギリスのラウンドが炭化珪素による発光現象を発見 |
| 1927年 | ソ連のローゼフが世界初のLEDを発表 |
| 1962年 | アメリカのニック・ホロニアックが赤色LEDを開発 |
| 1968年 | 黄緑色LEDが開発される |
| 1972年 | 黄色LEDが開発される |
| 1985年 | 橙色LEDが開発される |
| 1993年 | 実用的な高輝度青色LEDが開発される |
| 1995年 | 純粋な緑色LEDが開発される |
| 1996年 | 青色LED+黄色蛍光体による白色LEDが開発される |
| 2002年 | 紫外光LED(UV-LED)+RGB蛍光体による白色LEDが開発される |
最近になって登場した印象のあるLEDですが歴史は意外と古く、今から100年以上前に科学者ヘンリー・ジョセフ・ラウンドが、炭化ケイ素の塊に電流を流すと黄色く発光することを発見したことがLEDの始まりです。
その後1960年代にはすでに暗めの赤色と黄緑色が開発され、70年代には黄色も誕生。
LEDで白色、フルカラーを発光させるためには青色LEDが必要になり、青色LEDの開発には多くの
日本人が貢献しました。
1993年、ついに日本メーカーと日本人研究者により青色LEDが生み出され、これがLED発展の大きな転機となります!
なぜならこれで光の三原色(R赤 G緑 B青)が揃い、自由な色表現ができるようになったからです。
こうして家庭用のLED電球をはじめ、イルミネーション電飾、液晶ディスプレイ、自動車など幅広い商品にLEDの活躍の場が広がりました。
白熱電球や蛍光灯との違い
白熱電球、蛍光灯、LED、この3つの大きな違いは寿命です。
白熱電球の寿命は1,000~2,000時間程度、蛍光灯の寿命は13,000時間程度、LED電球の寿命は約40,000時間と言われています。
ではなぜ、ここまで大きく寿命が異なってくるのでしょうか。その主な理由となる発光原理の違いを順に見てみましょう。
白熱電球の光る仕組み

白熱電球はフィラメントと呼ばれる細い金属線(タングステンという金属が使用されています)を熱することで光を発生させる仕組みです。
電流を流すと2000℃以上の高温になって光を発し、温かみのある白熱光を生み出しています。
蛍光灯の光る仕組み

蛍光灯は、ガスが封入されたガラス管と、両端の電極(フィラメント)で構成されています。
この電極から電子を放出して、管の中にある水銀ガスに電子を衝突させます。
水銀ガスに電子が衝突すると紫外線が発生し、その紫外線と蛍光塗料(ガラス管内に塗ってあります)がぶつかることで発光します。
普段何気なく電気を点けていますが、蛍光灯の中ではこんな複雑なことが起きていたんですね!
LEDの光る仕組み

LEDは、P型(プラスの性質)と、N型(マイナスの性質)の2種類の異なる性質を持つ半導体を接合して作られています。
LEDに順方向の電圧をかけるとプラスはマイナスに、マイナスはプラスへと向かっていき衝突し、この衝突によって光が生まれます。
つまり、プラス(+)とマイナス(-)の電気がくっつくことによって発光します。
これが私達の目に見えているLEDの光であり、電気エネルギーを直接光に変換するという、従来光源にはない
優れた特徴です。
このように白熱電球や蛍光灯は、電気を一旦熱に変えてから光を発生させる仕組みで、最初に熱を発生させるための電力を必要とします。
一方でLEDは流れる電気そのものを直接光に変換する仕組みなので、とても効率が良いのです。
なぜLEDが普及しているのか
東日本大震災による原子力発電所の停止、そして電力不足。
この出来事をきっかけに日本政府のLED化の活動が本格的に始まりました。
省エネ改革や、「水銀に関する水俣条約」の締結であったり、LED化補助金制度などにより商業施設やオフィスを中心に、LED化が進んでいます。
(「水銀に関する水俣条約」 に関しては以下記事でも解説しています)
最近だと、築年数が古いマンション共用部の照明がLED化されているのもよく見かけますね。

おしゃれなカフェやバーなどで見るこのような電球も一見すると、「白熱電球かな?触ったら熱そう!」と思いがちですが、最近は白熱電球風のLEDも多いです。
そのため実際には熱くならず、節電しながらおしゃれな雰囲気を出せるようになりました。
少しずつ私達の身近な部分でのLED化が進んでますね!
照明・電材・工具の通販サイト「メガランプ」では、記事内で紹介した商品なども含め、16万点以上を取り揃えております。
最大で定価の80%OFFとなっておりますので、ご希望の商品をお安くお買い求めできるチャンスですよ!



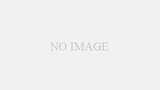
コメント